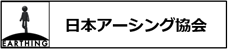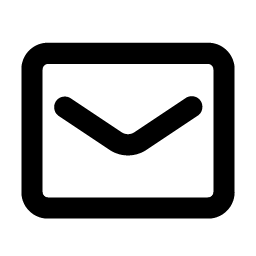最新アーシング研究論文/レポート情報
―― 科学的に信頼できる3つの論文を紹介します ――
今回は、2023年以降に発表されたアーシングに関する信頼性の高そうな学術論文を1本と、最近引用率の高い11、15年の論文2本を改めてご紹介します。
① ストレスによる不安行動に対する効果(動物実験)
-
論文タイトル:The Effect of Earthing Mat on Stress‑Induced Anxiety‑like Behavior and Neuroendocrine Changes in the Rat
-
発表年:2023年
-
掲載誌:Biomedicines(査読付き)
-
ポイント:
ストレスを与えたラットにアーシング環境を与えたところ、明らかに不安行動が減少し、脳内のストレス関連ホルモン(CRF)の発現も抑制されました。企業名や商品名は一切使われておらず、純粋な学術研究として信頼性が高いと思います。
アーシングに関心のある方の間では、「コルチゾール(ストレスホルモン)」の正常化はよく知られた効果のひとつです。実際に、過去の研究ではアーシングが日内リズムに沿ったコルチゾールの分泌パターンを回復させることが報告されてきました。
今回ご紹介している2023年のラット実験(Biomedicines誌)では、そのさらに「上流」にあるストレス応答因子、**CRF(コルチコトロピン放出因子)**の発現が、アーシングによって有意に抑制されたことが示されています。
CRFは、視床下部から分泌されるホルモンで、ACTHを介して副腎からのコルチゾール分泌を引き起こす引き金となる物質です。
つまり、この研究は「アーシングがCRFレベルでストレス応答を鎮める」ことを示しており、従来の「コルチゾールが整う」効果の、より深い神経内分泌的な根拠を裏付けるものだといえます。
このように、アーシングは単なるリラクゼーションではなく、ストレスホルモン系(HPA軸)全体に穏やかな調整効果をもたらす可能性があることが、段階的に明らかになってきています。
論文リンク:
https://www.mdpi.com/2227-9059/11/1/57
② アーシングが生理学的プロセスに及ぼす影響(人間研究)
-
論文タイトル:Earthing the Human Body Influences Physiologic Processes
-
発表年:2011年(現在も多数の論文に引用)
-
掲載誌:Journal of Alternative and Complementary Medicine(査読付き)
-
ポイント:
「Earthing the Human Body Influences Physiologic Processes」(2011年)は、人が大地と導通した際の生理変化を検証した査読付き研究で、血液成分(鉄、カルシウム、甲状腺ホルモン、血糖など)の変化が観察されました。アーシングは炎症を抑え、ホルモンバランスや血糖値を安定させる可能性があり、特に慢性ストレスや代謝異常への応用が期待されています。利益相反はなく中立的な立場で実施されており、その後の皮膚血流・ストレス応答・炎症マーカーに関するRCTやレビュー論文にも多数引用されています。アーシングは日常的な健康習慣として注目され始めていますが、まだ検証段階であり、今後の大規模研究が求められています。
論文リンク:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3154031/
③ 理論と生体電気的メカニズムの整理(レビュー)
-
論文タイトル:The Biophysics of Earthing: Human Health Implications of Reconnection with the Earth’s Electrons
-
発表年:2015年(現在も環境医学や教育分野で引用多数)
-
掲載元:学術書章(CRC Press 収録)
-
ポイント:
「The Biophysics of Earthing: Human Health Implications of Reconnection with the Earth’s Electrons」は、人と地球との電気的な接続が生理機能や健康に及ぼす可能性を体系的に整理したレビュー論文です。歩行や就寝時の地面との導通が、コルチゾールリズムの正常化、疼痛の軽減、睡眠の改善、炎症反応の抑制につながるという所見を提示しています。
この論文は、2012年にJournal of Environmental and Public Healthに掲載され、公表後すでに200件以上の引用が確認されており、関連分野での影響力が高いことがわかります。
引用先としては、炎症・免疫応答・創傷治癒に関する研究(Oschmanら、2015年)、RCTによる血流や血液粘度測定研究、統合的健康レビュー論文など、多様な形式で活用されています。
理論的背景と複数の実験・観察結果を統合しており、代替医療・環境医学系の研究者に一定の評価を受けています。
ただし、内容には代替医療寄りの仮説も含まれており、メインストリームの臨床医学からは懐疑的な見方もあることに留意する必要があります 。